ドラマ「三国志外伝ー愛と悲しみのスパイ」は諸葛亮孔明が亡き劉備の遺志を継ぎ、漢王朝復活のために北伐を決意。
その第一次北伐が失敗に終わったことから物語が始まります。
スパイの誤情報が失敗の理由のひとつ。
裏切り者は誰だ?
この記事ではドラマ「三国志外伝ー愛と悲しみのスパイ」その後の三国志について、北伐はどうなったのか?
調べてみました。
北伐はどうなったのか?ドラマと史実の違い
「三国志外伝ー愛と悲しみのスパイ」では、街亭の戦いで敗れ、第一次北伐は失敗に終わり、その後第二次北伐で蜀は隴右(ろうゆう)の隠平(いんぺい)・武都(ぶと)を奪回したような描き方思います。
これは史実ではどうだったのでしょうか?
奪回するとあると、成功した、勝利したように思います。
でも、実はこの戦いは第二次北伐だとは言えないようです。
というよりは、これは第一次北伐です。
ドラマだと、新たに北伐を開始した、第二次北伐で隴右(ろうゆう)の隠平(いんぺい)・武都(ぶと)を奪回したような描き方に感じます。
しかし、史実から考えると、第一次北伐において、街亭は奪われたけれど、隴右の隠平郡・武都郡を奪回できた。
大敗の中にも勝利するところもあった、ということ。
つまり街亭の戦いでの敗北と隠平・武都奪回は連続した出来事、同じ年の出来事です。
確かに、「三国志外伝ー愛と悲しみのスパイ」も何年もの期間の話ではないですね。
私ははじめ見ていたときは、しばらくたっての戦いと感じてしまいました。
きっと、ドラマ的に蜀が最後希望ある終わり方をしたかったのではないでしょうか?
主人公:陳恭の死を無駄にしては悲しいですものね。
陳恭はすべての罪を自分が背負うような形で処刑され亡くなりました。
この結末、これは蜀を守るため、漢復興のためでもあります。
この死を無駄にしないためにも、蜀に希望のある終わり方でなければ悲しい。
史実に基づきながらもドラマチックに脚本していくドラマ。
その中から史実を読み解く楽しさ。
これが歴史ドラマの良いところですね。
隴右はどこにあるの?
隴右(ろうゆう)は隴山の右に位置し、長安から見て西にある 隴山(ろうざん)一帯を指します。
あれ?「隴」は「隴西(ろうせい)」の「隴」。
そうです、「隴」とは中国西方にある隴山(ろうざん) を言います。
隴右(ろうゆう)は魏と蜀の国境の山岳地帯で、武都・隠平・天水・隴西などを含むのです。
つまり、隴右という広い地方の中に隴西という群があって、その隴西の中に街亭があるのです。
成都(蜀の都)→武都・隠平(国境の砦)→長安(魏の都)
このルートから考えると、武都・隠平は蜀にとっても、魏にとっても重要な場所ですね。
蜀にとっては、北伐に必ず通る地域になります。
この場所の奪回は蜀にとっては大きな意味をもちますね。
そして、魏にとってこの場所は西の防衛線。
ですから、奪われてしまったのは痛手です。
ですから、ドラマでは、蜀がこの隠平・武都奪回は北伐の勝利に向けて、希望の光となったのです。
そうして、ドラマがしめくられたのですね。
あれ?でもこの場所は、もともと魏の領土だったはず…。
奪回って?
もともと蜀の土地を魏に奪われていたのでしょうか?
武都・隠平はもともと蜀の土地だった?
さて、武都・隠平を奪還というと、もともとは蜀の土地だったということでしょうか?
武都・隠平は漢王朝が衰退すると、戦乱ののたびに勢力が入れ替わっていたようです。
そして、魏や蜀の国境に近い隴右の中の武都・隠平は、魏の勢力が強かった。
でも、住民や豪族の一部は蜀との結びつきが強かったようです。
地理的には蜀に近いですからね。
ですから、もともと蜀の土地ではないのです。
後漢末から三国の戦乱で魏に奪われたという感覚なのでしょうか?
劉備は漢王朝の血を引く人物。
ですから、「漢室の正統な後継者」、その劉備の遺志を継ぐ諸葛亮孔明。
武都・隠平は蜀にとっては自分たちの領土という想いがあるのだと思います。
漢の土地を取り戻すのです。
この時代は、すでに漢王朝は滅亡。
後漢の献帝が220年、曹操の息子曹丕に禅譲し魏の時代。
蜀からみたら、魏は漢王朝を奪った国です。
北伐は、漢王朝復興のためなのです。
だから、奪還なのですね。
その後の北伐の現実
さて、「三国志外伝ー愛と悲しみのスパイ」では、蜀が領土の位置を奪い返した。
と希望の光を感じさせています。
では、結局北伐はどうなったのでしょうか?
この武都・隠平を奪還で終わりではありません。
むしろ始まりです。
その後、第四次・第五次北伐と続きますが、なかなか勝利には結びつきません。
第三次北伐では兵糧不足で撤退をしています。
諸葛亮孔明も苦悩の連続だったと思います。
そして、最後の第六北伐でついに諸葛亮孔明が病気で亡くなり、北伐は志半ばで終わってしまうのです。
さて、魏にはこの時期、司馬懿(しばい)がいます。
司馬懿は軍師というよりは天才戦略家とでもいうのでしょうか。
諸葛亮孔明と司馬懿の頭脳戦も三国志の楽しみです。
その司馬懿が本格的に登場するのは、第三次北伐のころ。
そして第六次北伐の「五丈原」の戦いで234年諸葛亮孔明が病死するのです。
諸葛亮孔明の死は、しばらく内緒にしていました。
これは彼の最期の戦略です。
諸葛亮孔明の死後、蜀軍は撤退していきます。
でも生きているように見せかけたのです。
亡くなったと魏にわかれば、猛攻撃されますかね。
司馬懿は、諸葛亮孔明の死を疑いつつ、でも罠かもしれないと追撃をためらいました。
その間に蜀は逃げたのです。
後に、すでに諸葛亮孔明が亡くなっていたことをしった司馬懿が残した言葉
「死せる孔明、生ける仲達を走らす」
亡くなった孔明の策略にまんまとはまり、生きている自分が振り回された。
仲達とは司馬懿のことです。
司馬懿は慎重派です。
そんな性格も知っている諸葛亮孔明の戦略だったのでしょう。
最期まで、蜀のために策をめぐらせた、まさに天才軍師です。
それでも漢王朝は復興できなかったのですね。
と、これが「三国志外伝ー愛と悲しみのスパイ」のその後です。
いかがでしたでしょうか?
「三国志外伝ー愛と悲しみのスパイ」から、三国志の世界、しかも劉備や曹操も亡くなったその後の世界をのぞいてみるのも楽しいですね。
三国志は難しい、そしてむさくるしい。
そんなイメージもありますが、楽しく歴史を学ぶきっかけになると思います。

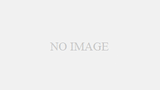
コメント