「三国志ー外伝愛と悲しみのスパイ」ご覧になりましたか?
このドラマで登場する『五仙道』
一体どんな組織か気になりませんか?
実際に存在する組織なのか?
このあたりを調べてみました。
「三国志外伝ー愛と悲しみのスパイ」五仙道は実在した?
「三国志外伝ー愛と悲しみのスパイ」このドラマの中盤で重要な役割を果たす五仙道(ごせんどう)。
陳恭(ちんきょう)の妻である翟悦(てきえつ)が、潜入している組織です。
実際に存在したのか?
結論から言えば架空の組織です。
史実の三国時代には「五仙道」という組織は存在しません。
ただ、そのモデルとなった組織が存在していたようです。
それが、後漢末期に実在した宗教団体「五斗米道(ごとべいどう)」です。
五斗米道は、後漢末期に誕生した宗教組織です。
米を五斗(約10リットル)寄進すれば入信できることから、この名がついたとされているようです。
米五斗は、一家の数か月分の主食のお米に相当したようです。
当時の感覚では、少し無理しなければ差し出すことができなかった量だと思います。
それでも入信する魅力があったのでしょう。
混乱の時代、宗教に頼りたかったのでしょうか?
どんな組織だったのか気になりますね。
しかも、ドラマの中の「五仙道」、怪しげでしたよね。
実際に存在した「五斗米道」も怪しげだったのでしょうか?
「三国志外伝ー愛と悲しみのスパイ」の中で描かれた「五仙道」という組織は存在していませんが、モデルとなった宗教団体は存在しています。
でも、宗教組織がなぜ、この三国志に争いに関与しているのでしょうか?
宗教団体ならば、平和に中立の立場ではないの?
「五斗米道」がどんな組織だったのか気になってきましたね。
「五斗米道」とは、どんな組織だったのか?
「三国志外ー伝愛と悲しみのスパイ」で登場するミステリアスな組織「五仙道」。
そのモデルとなった「五斗米道」とは、いったいどんな組織だったのでしょう?
「五斗米道」は三国時代の魏と蜀の間の戦いにおいて、非常に重要な間接的な影響を与えています。
まず、五斗米道は、教主の張魯(ちょうろ)が治める漢中(かんちゅう)を拠点としていました。
不老不死や病気の祈祷を重要視していたようです。
となると、ドラマの中で翟悦が来ていた衣装やミステリアスな踊りも納得できますね。
そして、戦乱の時代において、信者たちの生活を支えていたようです。
しかし、そんな宗教組織がなぜ、魏と蜀の争いの関与する「五仙道」のモデルになっているのでしょうか?
実際に「五斗米道」も政治と接点があったのでしょうか?
漢中は、北へ行けば関中・洛陽と曹操の本拠地、そして南に行けば蜀の劉備の本拠地という場所に位置しています。
つまり、魏と蜀を分ける喉元なのです。
ですから、曹操も劉備も喉から手が出るほど欲しい土地だったのです。
そしてこの「五斗米道」、実はただの宗教団体ではなく、宗教を基盤にした小国家だったようです。
教主の張魯(ちょうろ)は決して大きな帝国を築こうとしたわけではなく、漢中という土地をまとめたかっただけかもしれません。
でも地理的に魏と蜀のはざまではどうすることもできず、曹操に降伏したようです。
漢中だけで独立した国家を築くのは難しい。
そう判断したのかもしれません。
つまり、張魯が漢中に独立勢力を築いていたことは確かなようです。
そして、その存在が魏と蜀の双方にとって戦略的な思惑の対象となっていたのです。
彼らは三国時代の争いにおいて、スパイ活動を行っていたという事実はありません。
あくまでも地理的に重要な場所であったために巻き込まれた、と言ってもいいのかもしれません。
というわけで、「五仙道」のモデルとなった宗教組織「五斗米道」。
ドラマで描かれているような組織ではなかったのでしょう。
ただ、地理的な要因と、小国家という組織が政治に関与したのは間違いないようです。
「三国志外伝ー愛と悲しみのスパイ」での「五仙道」とは、どのような組織だったのか?
「三国志外伝 愛と悲スパイ」における五仙道は、単なる宗教団体ではありません。その最大のポイントは、魏の間諜(スパイ)組織、特に「燭龍」の拠点の一つとして機能していたという点です。
主人公・陳恭が、魏の間諜である糜冲(びちゅう)になりすまして潜入するのが、この五仙道でした。
彼らは、主に魏の間軍司(情報機関)の幹部、そして糜冲などの魏の間諜と連絡をとりあっていました。
五仙道は、魏のために情報収集や攪乱工作を行っており、このドラマの中では重要な組織です。
そして、ただのスパイ組織としてでなく、独特の雰囲気や思想がこのドラマに良いスパイスを与えていると思います。
翟悦の踊りや儀式は、ドラマ「三国志外伝 愛と悲しみのスパイ」の中でも特にミステリアスで印象的に感じました。
三国志の物語というと、男たちの戦いや策略が中心。
この「三国志外伝 愛と悲しみのスパイ」も地味な衣装で髭を生やした男性陣の緻密な駆け引きの中で、神秘的な幻想的な雰囲気が加わり、見入ってしまうシーンだと感じます。
その怪しさが、ただのスパイドラマではないエッセンスになっていると感じます。
「三国志外伝ー愛と悲しみのスパイ」での「 翟悦」の存在意義
翟悦(てきえつ)の存在は、物語の核心に深く関わっており、彼女の死は主人公・陳恭に計り知れない影響を与えました。
彼女の死は、単なる悲劇ではなく、物語全体のテーマを浮き彫りにする非常に大きな意味を持っています。
救いだそうとした陳恭、しかしそれを拒み死を選んだ妻・翟悦。
スパイとしての悲劇的な運命を象徴するシーンですね。
翟悦の死は、陳恭の今後の行動や心境に、決定的な影響を与えました。
復讐心と使命感、そして自分は何者なのか?
翟悦は、陳恭にとって単なる妻ではなく、彼の心の拠り所であり、任務を続ける原動力でもありました。
回想シーンに陳恭のそんな思いを感じとれます。
彼女の壮絶な死は、私たち視聴者に強い衝撃を与えます。
スパイ活動の裏にある、ひとりの人間としての抑えていた感情が浮き彫りになったように感じました。
そして、これが邦題のサブタイトル「愛と悲しみのスパイ」につながるのですね。
「三国志外伝ー愛と悲しみのスパイ」は男性陣多め、女性陣の登場は少なめ。
でもだからこそ、翟悦の存在はこのドラマにとって大きな意味を持ちます。
恋愛ドラマという軽さはありません。
でも愛する人と、ただ普通に暮らすことすらできない時代背景、スパイいう職業の悲しさ。
何を守り、何を犠牲にするのが正しいのか?
考えさせられるに、翟悦の存在は大きな意味をもちます。
いかがでしたでしょうか?
今回の記事では「三国志外伝ー愛と悲しみのスパイ」に登場する「五仙道」について深堀してみました。
中国ドラマは史実をもとに脚本し、非常に深みのあるドラマにしあげているのも魅力の一つだと感じます。
ぜひ、史実との比較を楽しんでいただけたら嬉しいです。

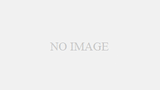
コメント